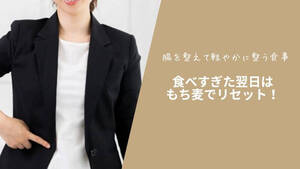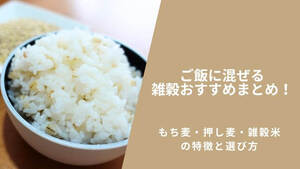疲労回復にぴったりな食べ物|もち麦を使った食事で疲れが抜けないから抜け出そう!

「寝ても疲れが取れない」「体が重くてやる気が出ない」——。
そんな“抜けない疲労感”を感じていませんか?
その原因は、睡眠不足だけではなく、エネルギーをつくるための栄養不足や腸内環境の乱れにあるかもしれません。
疲労をためない体をつくるには、毎日の食事で“代謝と腸”を整えることがポイント。
この記事では、疲労感が抜けない理由と、疲労回復をサポートする食べ物として注目の「もち麦」をご紹介します。



さらに、もち麦と組み合わせるとより効果的な食事例やおかずも紹介します。
疲労感が抜けない理由とは?


「疲れが取れない」と感じるとき、体はエネルギー不足の状態になっています。
一見元気そうに見えても、体の中では栄養のバランスが崩れ、代謝がうまく働いていないことが多いのです。
① エネルギーを作る栄養が不足している
疲労回復には、糖質・脂質・たんぱく質をエネルギーに変えるビタミンB群が欠かせません。
しかし、偏った食事や外食が続くと、ビタミンB1・B6・B12が不足しやすく、疲れやすい体に。
② 腸内環境の乱れ
腸の状態が悪くなると、栄養の吸収がスムーズにいかず、エネルギーを十分に取り込めなくなります。
さらに、腸と脳は密接に関係しており、腸内環境の乱れは“だるさ”や“やる気の低下”にもつながります。
③ 血糖値の急上昇による倦怠感
食事で血糖値が急に上がると、インスリンの働きで今度は急降下。
この変動が激しいと、食後に眠気やだるさを感じることがあります。



ごはんを食べると余計に疲れる気がする…
という人は、血糖コントロールも意識したいところです。
疲労回復には「食べ方」も大切


疲れをためない体にするためには、何を食べるかだけでなく、どう食べるかも大切です。
朝食を抜かない
朝ごはんは、体内時計をリセットし、代謝をスムーズにするスイッチ。
もち麦入りごはんやスープなど、軽くてもエネルギー源になる食事をとりましょう。
バランスの取れたプレートを意識
炭水化物・たんぱく質・野菜をそろえることで、栄養の吸収が高まり、体が軽く感じやすくなります。
特にたんぱく質は、筋肉やホルモンの材料となり、疲れにくい体を支える基本です。
血糖値をゆるやかに上げる食材を選ぶ
白米よりも低GIのもち麦や玄米、野菜・きのこ類を組み合わせることで、エネルギーが安定し、だるさを感じにくくなります。
もち麦が疲労回復にぴったりな理由


もち麦は、腸を整えながら代謝を高める、まさに“疲労回復向けの主食”です。
ビタミンB群がエネルギー代謝をサポート
もち麦にはビタミンB1・B6が含まれており、糖質を効率よくエネルギーに変えるサポートをします。
この働きにより、「疲れやすい」「集中力が続かない」状態から抜け出しやすくなります。
β-グルカンで腸内環境を整える
もち麦の最大の特徴は、水溶性食物繊維β-グルカンが豊富なこと。
腸内の善玉菌をサポートし、腸内フローラを整えることで、体全体のリズムを整えます。
腸が整うと栄養の吸収もスムーズになり、エネルギーを効率よく使える体に。
血糖値の上昇をゆるやかにして“だるさ”を防ぐ
もち麦は白米よりも糖質が控えめで、血糖値の上昇をゆるやかにします。
その結果、食後の眠気や倦怠感が起こりにくくなり、午後のパフォーマンスも安定。
腹持ちがよく、間食を防げる
もち麦はしっかり噛む必要があるため、自然と満腹感が得られます。
お菓子や甘い飲み物を減らせることで、エネルギーのムラがなくなり、疲れを感じにくくなります。
もち麦と相性の良い疲労回復おかず


もち麦は、どんなおかずにも合いやすいのが魅力。
疲労回復を狙うなら、次のようなメニューと組み合わせるのがおすすめです。
豚肉のしょうが焼き
豚肉にはビタミンB1が豊富に含まれ、糖質の代謝を助けて疲労回復をサポート。
しょうがの香りが食欲を引き出し、体を温める効果も期待できます。
鮭の塩焼き
鮭に含まれるアスタキサンチンは抗酸化作用があり、細胞の疲れをやさしくケア。
もち麦ごはんとの相性も抜群で、消化にもやさしい組み合わせです。
納豆+温泉卵
たんぱく質とビタミンB群を一度にとれる“疲労回復コンビ”。
腸内環境を整え、朝食にもぴったりな栄養バランスです。
ブロッコリーとツナの和え物
ブロッコリーに含まれる鉄分やビタミンCが、ツナのたんぱく質吸収を高めます。
もち麦ごはんと一緒に食べることで、バランスのよいワンプレートに。
もち麦を使った簡単疲労回復レシピ
もち麦と豚肉の生姜スープ
体を温めながらエネルギー代謝を高める、冬にぴったりのスープ。
もち麦を入れることで腹持ちもアップし、夜食にもおすすめです。
もち麦と鮭のチャーハン
鮭のたんぱく質ともち麦の食物繊維で、腸から元気をチャージ。
お弁当にも使える万能メニューです。
もち麦と納豆のとろろごはん
腸内環境を整える発酵食の組み合わせ。
ネバネバ食材との相性も良く、胃腸が疲れている日にも◎。
疲労をためない「もち麦習慣」のコツ
- 白米に2~3割もち麦を混ぜて炊く:自然に食物繊維とビタミンを補給
- 茹でもち麦を冷凍ストック:スープやおかずにサッと加えられる
- 朝食でもち麦スープを取り入れる:腸を目覚めさせて代謝アップ
もち麦は手軽に続けられる“整え食材”。
食べるたびに、体の中から少しずつエネルギーが満ちていく感覚を実感できるでしょう。
まとめ
「疲れが取れない」「だるさが抜けない」と感じるときこそ、食事で整えるチャンスです。
もち麦は、
- ビタミンB群で代謝をサポート
- β-グルカンで腸内環境を整える
- 血糖値を安定させて倦怠感を防ぐ
という3つの働きで、疲労回復をやさしく支えてくれます。
さらに、豚肉や鮭、納豆など疲労回復に役立つおかずと組み合わせれば、自然と“疲れが抜けるごはん”に。
もち麦を毎日の食事に取り入れて、心も体も軽やかに過ごしましょう。
食物繊維、足りてますか?
現代人は食物繊維が不足気味💦
男性:21g以上 / 女性:18g以上 が推奨量!
でも実際は…
男性で平均15.3g / 女性で平均14.7gと不足しているんです💡
もち麦50gなら約5gの食物繊維を摂取可能✨
腸内環境を整えてより健やかな毎日を送りませんか?
山藏農園の有機栽培もち麦500gを一日50g食べるなら…


1カ月当たり約3袋あればOK!
または…
食物繊維いっぱいのおかずと一緒に取り入れるなら…


もち麦約25g…食物繊維約2.5g摂取
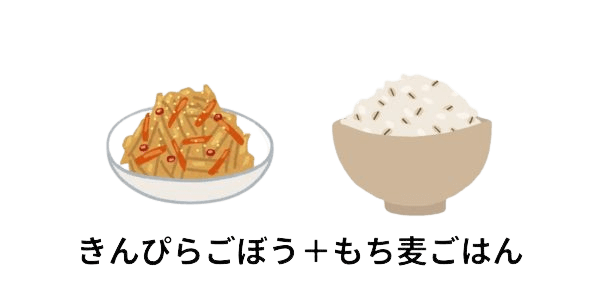
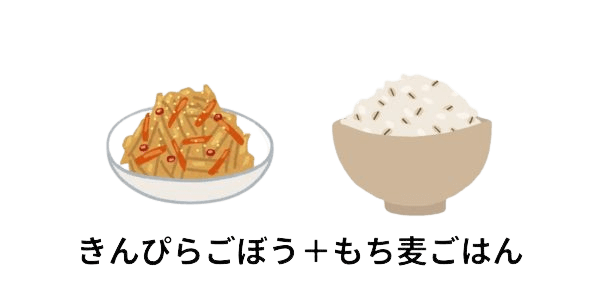
もち麦約25g…食物繊維約2.5g摂取
で、食物繊維の摂取目標に近づけることができます!(※参考:カロリーslim)
山藏農園の有機栽培もち麦500gを一日25g食べるなら…
1カ月当たり約1.5袋!
3週間に1袋のペースでOK!



定期便なら、お買い物の手間も省け、買い忘れもなく便利です
もち麦を生活に取り入れて、健康習慣を手に入れませんか?