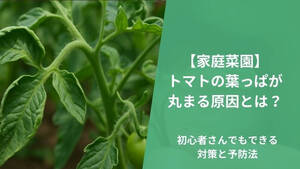【保存版】家庭菜園で種からミニトマトを育てる全手順と管理のポイント




ミニトマトを種から育ててみたいけど、難しそう…
そんな不安を持っていませんか?



実は、種からミニトマトを栽培するのは想像よりもずっと簡単で、大きな喜びを得られるものです。
市販の苗より低コストで始められるうえ、発芽の瞬間から収穫までの全過程を体験できる家庭菜園の醍醐味があります。
この記事では、初めての方でも失敗しないよう、種の選び方から収穫までの手順を分かりやすく解説します。
特に重要なポイントや初心者がつまずきやすいところは丁寧に説明しますので、安心してチャレンジしてください。
今年の夏は、自分で種から育てた甘くて新鮮なミニトマトを家族に振る舞いませんか?
さあ、家庭菜園の新たな楽しみを一緒に始めましょう!
種からミニトマトを育てるメリット
種からミニトマトを育てるメリットはたくさんありますが、今回は下記の3点について注目してみましょう!
- 経済的なメリット
- 栽培の喜びと満足感
- 自家採種の達成感
経済的なメリット


種からミニトマトを育てる最大の魅力の一つは、経済的なメリットです。
市販のミニトマトの苗は1ポット当たり100円から300円程度します。接ぎ木のものだと300円から600円前後のものもあります。
種の場合は1袋500円前後でたくさんの種が入っていることがほとんど。
単純計算でも1株あたりの値段を考えると、大幅なコスト削減になります。
特に複数のプランターや広い畑でたくさんの株を育てたい場合、苗で揃えると数千円以上の出費になりますが、種からならわずかな費用で済ませることができます。
また、種から育てることで、発芽率や生育状況を見ながら必要な株数だけを選別できるため、無駄なく効率的に栽培を進められるのも経済的なポイントです。



余った種は適切に保存すれば次のシーズンにも使用できますので、一度の投資で長く楽しむことができます。
ミニトマトの種は、適切に保存すれば2〜3年は発芽能力を維持します。(プライミング処理されているものの場合)
乾燥した種を紙の袋やジッパー付きの小袋に入れ、冷蔵庫の野菜室などの低温で乾燥した場所に保管する。湿気を避けることが重要なポイントです。
長期保存した種は発芽率が少し下がることがありますが、その分多めに播種すれば問題ありません。
また、複数品種の種を保存しておけば、シーズンごとに異なる品種を育てたり、同時に複数品種を育てて食べ比べたりと、楽しみ方も広がります。
種の保存は単なる経済的メリットだけでなく、自分好みの品種を長く継続して育てられる利点もあります。
市場の流行に左右されず、自分が美味しいと感じた品種を何年も続けて栽培できるのは、種から育てる大きな魅力の一つです。
栽培の喜びと満足感


種からミニトマトを育てる最大の醍醐味は、小さな種が発芽し、成長して実をつけるまでの全プロセスを見守れることです。



小さな芽が土から顔を出した瞬間はとても感動します…!
その後、本葉が出て、茎が伸び、花が咲き、実がなるまでの変化を日々観察できるのは、苗から始める栽培では味わえない特別な体験です。
特に子どもと一緒に育てる場合は、生命の神秘や成長の過程を学ぶ素晴らしい教材になります。
種をまいた日、発芽した日、花が咲いた日、最初の実がなった日などを記録していくと、自然のサイクルを実感できるでしょう。
また、毎日の変化を写真に撮って記録すれば、成長の過程をより実感できますし、SNSで共有すれば同じ趣味を持つ人との交流も広がります。
小さな種から自分の手で大切に育て上げたミニトマトの初収穫は、格別の味わいがあります。
スーパーで買ったものとは比較にならない新鮮さと、愛情を込めて育てた満足感が味わいに深みを加えます。
ミニトマトの種の選び方


ミニトマトには数多くの品種がありますが、種から育てる初心者には栽培が比較的容易で失敗が少ない品種がおすすめです。



「千果」や「アイコ」などの定番品種は、発芽率が高く生育も安定しているため、初めての栽培でも成功しやすいでしょう。
「ミニキャロル」は小ぶりながら甘みが強く、病気にも強い特性があります。
「サンチェリー」は高温多湿にも比較的強く、日本の夏でも育てやすい品種です。
「ピッコラルージュ」は小粒ながら糖度が高く、収穫量も多いため満足度が高い品種といえます。
初心者は複数の品種を少量ずつ育ててみて、自分の環境やケア方法に合った品種を見つけるのも良い方法です。
種のパッケージには栽培の難易度や特徴が記載されていることが多いので、
- 「初心者向け」
- 「病気に強い」
- 「高収量」
などのキーワードを参考に選ぶと良いでしょう。
病気に強い品種の特徴
ミニトマトの栽培で悩ましいのが病気の問題です。
特に初心者は病気に強い品種を選ぶことで、栽培の成功率が大きく上がります。
近年は育種技術の発達により、病気に強い抵抗性品種が多数開発されています。
パッケージに「耐病性」「○○病抵抗性」などと表記されている品種は、その病気に対して強い抵抗力を持っているので、チェックしておきたい部分です。
また、地域の気候に適した品種を選ぶことも重要です。
例えば、高温多湿の地域では耐暑性の高い品種を、冷涼な地域では低温でも結実する品種を選ぶと良いでしょう。
地元の園芸店で人気の品種は、その地域の気候に適していることが多いので、参考にするとよいでしょう。



最近の品種はどんな気候でも栽培することができるオールラウンダーな品種も多いです。
種の入手方法|園芸店やオンラインでの購入


ミニトマトの種は、ホームセンターや園芸店、農業資材店などで簡単に入手できます。
実店舗で購入する利点は、店員さんからアドバイスがもらえることや、その地域の気候に合った品種が揃っていることです。
また、発芽に必要な培養土や肥料なども一緒に購入できて便利です。
一方、オンラインショップでは、実店舗よりも多くの品種から選べる利点があります。
珍しい固定種や海外の品種なども入手しやすく、口コミやレビューを参考にすることもできます。
大手種苗メーカーの公式オンラインショップや、園芸専門のネットショップなどがあります。
種を購入する際は、発芽率を左右する鮮度を確認することが重要です。
パッケージに記載されている「発芽率」や「有効期限」は必ずチェックしましょう。
一般的には、新しく採種された当年の種が最も発芽率が高いですが、トマトの種は、適切に保存されていれば2〜3年前の種でも問題なく発芽することが多いです。
また、環境に配慮した有機種子やハイブリッドではなく固定種を取り扱う専門店も増えています。
種まきから発芽までの手順。最適な時期と環境とは?
家庭菜園でミニトマトの種まきをするにあたり、
- 種まきの時期
- 種まきの環境
- 種まきの具体的な方法
をまとめています。参考にしてみてください。
地域別の種まき時期
ミニトマトの種まき時期は地域の気候によって異なります。
基本的には最終霜の時期を基準に考えます。
- 北海道など寒冷地では3月下旬から4月上旬
- 東北・北陸地方では3月中旬から下旬
- 関東・中部・関西地方では2月下旬から3月中旬
- 九州・四国・南西諸島では2月上旬から中旬



一概に言いづらいですが「桜の咲く季節」くらいですね。
ただし、これはあくまで目安であり、その年の気候や栽培環境によって調整が必要です。
室内で育苗する場合は、最終霜の日から逆算して6〜8週間前に種をまくのが理想的です。
これにより、定植時期には適切なサイズの苗に育っているでしょう。
また、秋まきを行う地域もあります。
暖地では8月下旬から9月上旬に種をまくことで、秋から冬にかけて収穫することができます。
ただし、秋まきは夏の高温期の育苗となるため、遮光や温度管理にはより注意が必要です。
地域の園芸店や農協で推奨される時期を確認したり、地元の園芸愛好家のブログやSNSを参考にするのも良い方法です。
気候変動の影響で従来の時期よりもずれることもあるため、最新の情報を確認することをおすすめします。
理想的な発芽環境の整え方


ミニトマトの種が最も発芽しやすい温度は20〜30℃です。
この温度範囲を維持することで、播種後5〜10日程度で発芽します。
室温が低い時期は、発芽を促進するためにシードヒーターや温室、保温マットなどを使用することも有効です。
湿度も発芽に重要な要素です。
種まき後の土は乾燥させないよう、常に湿った状態を保ちます。
ただし、水のやりすぎは腐敗の原因になるため注意が必要です。
播種後はラップや透明なドーム、ビニール袋などで覆って湿度を保つ方法も効果的です。
光は発芽そのものには不要ですが、発芽後すぐに明るい場所に移さないと徒長(ひょろひょろと弱々しく伸びること)の原因になります。
発芽が確認できたら、すぐに明るい場所に移しましょう。
窓際の日当たりの良い場所や、蛍光灯や植物育成用LEDライトの下などが適しています。
空気の循環も重要です。
発芽後は徐々に換気を行い、湿度を下げていきます。
これにより、苗が丈夫に育ち、病気のリスクも減少します。初めのうちは短時間の換気から始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。
種まきの具体的な方法


土と容器の準備
種まきには、清潔で水はけの良い育苗用の培養土を使用します。



市販の「種まき用培養土」が最適ですが、「野菜用培養土」でも構いません。
重要なのは、雑菌や雑草の種が混入していない清潔な土であることです。
容器は浅型のプラスチックトレイ、セルトレイ、小さな鉢、牛乳パックを切ったものなど、排水穴のあるものが適しています。
特に初心者は、セルトレイのように区切られた容器を使うと、後の移植が容易になるためおすすめです。
土を容器に入れる前に、底に軽石や鹿沼土を薄く敷くと排水性が向上します。
その上に培養土を8〜9分目まで入れ、表面を平らにならします。
次に、霧吹きなどで土全体を十分に湿らせておきます。
乾いた土に種をまくと、水やり時に種が流されてしまう恐れがあります。
また、種まき前に土を消毒することも、病気予防に効果的です。
沸騰させた熱湯を土にかけて冷ましたり、市販の土壌消毒剤を使用したりする方法があります。
ただし、市販の種まき用培養土はすでに消毒処理されていることが多いので、その場合は不要です。
播種の深さと間隔
ミニトマトの種は小さいため、播種の深さは5mm程度が適切です。
深すぎると発芽率が低下し、浅すぎると乾燥しやすくなります。



目安としては、種の2〜3倍の深さに埋める程度です。
播種方法には、点まき(一か所に1粒ずつまく)と条まき(溝を作って連続してまく)があります。
初心者には、後の間引きや移植が容易な点まきがおすすめです。
セルトレイを使用する場合は、各セルに1〜2粒ずつまきます。
発芽率の低い古い種の場合は、2〜3粒まいて確実に発芽させる方法も有効です。
種をまいたら、薄く土をかぶせるか、指で軽く押さえて種と土を密着させます。
その後、霧吹きで優しく水を与えます。強い水流で種が流されないよう注意しましょう。
播種後は、土が乾燥しないように透明なラップやビニールでカバーすると良いでしょう。
置き場所は暖かい場所が理想的ですが、直射日光は避けてください。
発芽までは日光は不要で、高温になりすぎると発芽率が低下する恐れがあります。
苗の育成と植え替えのコツ
種を植えた後、発芽してからどうしたらよいのかも押さえておきましょう!
- 発芽後の管理方法
- 植え替え
発芽後の管理方法


適切な水やりと日光の確保
ミニトマトの種が発芽したら、すぐにカバーを外し、十分な光を当てるようにします。
窓際の日当たりの良い場所か、蛍光灯や植物育成用LEDライトの下に置きましょう。
光が不足すると苗が徒長(ひょろひょろと弱々しく伸びること)するため、一日最低6時間は光に当てることが理想的です。
水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えるのが基本です。
頻繁に少量ずつ与えるよりも、土が乾いたタイミングでしっかりと与える方が根の発達を促します。
特に発芽直後は根がまだ弱いため、霧吹きなどで優しく水を与えると良いでしょう。
水やりのタイミングは朝が理想的です。
夕方や夜の水やりは、夜間の湿度が高くなり病気のリスクが高まります。
また、水の温度は室温に近いものを使用すると、根へのショックが少なくなります。
十分な通気性も重要です。
苗の周りで空気が循環することで、蒸れによる病気を予防し、茎が丈夫になります。
密集して育てている場合は、時々トレイの向きを変えるなどして均等に光が当たるようにしましょう。


間引きのタイミングと方法
一つのセルや鉢に複数の種をまいた場合、全てが発芽すると苗同士が競合して弱々しく育ってしまいます。
そのため、本葉が1〜2枚出てきた段階で間引きを行い、最も健康で丈夫な苗だけを残します。
間引きの方法としては、不要な苗を根元からハサミで切り取るか、ピンセットなどで慎重に引き抜きます。



引き抜く場合は、残す苗の根を傷つけないよう注意が必要です。
間引きのタイミングを逃すと、苗同士の根が絡み合って分離が困難になるだけでなく、残した苗にもダメージを与えてしまう恐れがあります。
また、苗が混み合うと風通しが悪くなり、病気のリスクも高まります。
間引き後は、残った苗に軽く水を与え、しばらく直射日光を避けて様子を見ましょう。
間引きによるストレスから回復したら、通常の管理に戻します。
鉢や畑への植え替え


植え替えの最適な時期
ミニトマトの苗の植え替え(鉢上げ)は、本葉が3〜4枚になった頃が適期です。
これは種まきから約3〜4週間後に相当します。
この時期の苗は、根がしっかりと発達しつつも、まだ柔軟で移植ショックから回復しやすい状態です。
季節と気候も考慮すべき重要な要素です。
屋外への定植(本植え)は、最終霜の危険がなくなり、夜間の気温が最低でも10℃以上安定する時期まで待ちましょう。
関東地方であれば4月中旬から下旬、北海道などの寒冷地では5月中旬から下旬が目安です。
植え替えは、曇りの日か晴れの日でも朝か夕方の涼しい時間帯に行うのが理想的です。



真夏日や強風の日は避けましょう。
また、植え替え後2〜3日は直射日光を避け、半日陰で管理すると移植ショックを軽減できます。
本葉の枚数だけでなく、苗の全体的な健康状態も確認しましょう。
茎がしっかりしていて、葉の色が濃い緑色であれば、植え替えのタイミングとして適しています。
逆に、徒長気味だったり、葉色が薄かったりする場合は、もう少し育苗環境を改善してから植え替えを検討しましょう。
植え替え時の注意点とトラブル防止
植え替え時のストレスを最小限にするために、いくつかの注意点があります。
まず、植え替え前日に十分に水を与えておくことで、根鉢が崩れにくくなります。
また、新しい鉢や畑の土も事前に水で湿らせておくと良いでしょう。
苗を抜く際は、なるべく根を傷つけないよう注意します。
セルトレイの場合は底から優しく押し上げるか、トレイ全体を軽くたたいて苗を浮かせると取り出しやすくなります。根鉢を崩さずに取り出せれば理想的です。
植え付ける深さも重要です。
トマト類は「深植え」が基本で、子葉の位置まで土に埋めるのが一般的です。
これにより、茎からも発根して丈夫な株に育ちます。



ただし、あまりに深植えしすぎると、土中の茎が腐る原因にもなるので注意が必要です。
植え替え後の管理としては、数日間は直射日光を避け、風通しの良い半日陰で管理します。
水やりは控えめにして、根が新しい土に馴染むのを待ちましょう。
移植ショックで一時的に萎れることがありますが、数日で回復するのが普通です。
回復後は徐々に日光に当てる時間を増やしていきます。
植え替え時の一般的なトラブルとして、根の乾燥や根の傷みがあります。
これを防ぐために、苗を抜いてから植え付けるまでの時間はできるだけ短くし、作業中も根を風や日光にさらさないようにしましょう。
必要に応じて、湿ったタオルやキッチンペーパーで根を包んでおくのも良い方法です。
収穫までの育て方と管理のポイント
収穫までには
- 水やり
- 追肥
- 害虫虫対策
などを行っていくことになります。
水やりと肥料の与え方


生育段階に合わせた水やり
ミニトマトの水やりは生育段階によって調整することが重要です。
定植直後は土が乾きやすいため、毎日もしくは1日おきに水を与えます。
根が十分に張った後は、土の表面が乾いてから水やりをする「乾湿交互」が基本となります。
生育初期(定植後〜花が咲くまで)は、根の発達を促すため、やや控えめの水やりが適しています。
土の表面が乾いたら、鉢底から水が出るくらいたっぷりと与えましょう。



この時期に水を与えすぎると、茎葉ばかりが成長し、根の発達が遅れる原因になります。
開花期から結実期にかけては、水分需要が高まります。
特に夏場は1日1回、朝に水やりをするのが理想的です。
ただし、水やりの頻度よりも、一度にしっかりと与えることが大切です。
浅い水やりを頻繁に行うと、表面根しか発達せず、乾燥に弱い株になってしまいます。
結実後、果実が大きくなる時期は最も水分を必要とします。
この時期に水分が不足すると、実割れや尻腐れ病の原因になります。



特に連日の猛暑日には、朝夕2回の水やりが必要になることもあります。
一方、収穫期が近づくと、水やりを少し控えめにすることで糖度の高い美味しいミニトマトに育ちます。
完全に水を断つわけではなく、土がやや乾燥気味になるよう調整しましょう。
水やりの方法としては、株元に直接水をかけるのではなく、株の周りの土に与えるのがベストです。
葉や茎に水がかかると、病気のリスクが高まります。特に夕方以降の水やりは、夜間の湿度を上げ病気を誘発するため避けましょう。


有機肥料と化学肥料の使い分け


ミニトマトの栽培では、肥料の種類と与え方が収穫量などに大きく影響します。



有機肥料と化学肥料はそれぞれ特徴があり、上手に使い分けることがポイントです。
有機肥料(堆肥、腐葉土、油かす、魚粉など)は効き目がゆるやかで持続性があります。
植え付け前の元肥として土に混ぜ込んでおくことで、長期間にわたって効果を発揮します。
有機肥料は土壌微生物の活動を活発にし、土の質を改善する効果もあるため、長期的な栽培には欠かせません。
一方、化学肥料は即効性があり、成分のバランスも調整しやすいのが特徴です。
生育期の追肥として利用すると効果的です。ただし、与えすぎると濃度障害を起こすリスクがあるため、説明書の量を守ることが重要です。
ミニトマトの栽培では、植え付け前に有機肥料をしっかり混ぜ込み、生育期には薄めの化学肥料を定期的に与える「併用法」が効果的です。
家庭菜園では、安全性と味を重視して有機肥料中心の栽培が人気です。
肥料のタイミングとしては、
- 植え付け時の元肥
- 開花時の追肥
- 結実期の追肥
という3回が基本です。
追肥は2週間〜1ヶ月に1回程度が目安ですが、生育状況を見ながら調整しましょう。
葉色が薄くなったり、新しい花の付きが悪くなったりした場合は、追肥のタイミングです。
液体肥料を使う場合は、水やりのついでに「水やり肥」として与えるのが簡単です。
この場合、濃度は通常の半分〜3分の1程度に薄めることがポイントです。
少量を定期的に与えることで、生育をムラなく安定させることができます。
追肥についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので是非参考にしてみてください。


病害虫対策と予防法
主な病気と対処法
ミニトマトを種から育てる際に悩まされがちな病気とその対処法を知っておくことは、栽培成功のカギとなります。予防が最も重要ですが、早期発見・早期対処も欠かせません。
最も一般的な病気の一つが「うどんこ病」です。



栽培後半に発生することが多いです。
葉の表面に白い粉のようなものが付着する特徴があります。
予防には風通しを良くすることが効果的で、発生初期には重曹水(水1リットルに重曹小さじ1)の散布が有効です。
症状が進行した場合は、園芸店で販売されている専用の薬剤を使用しましょう。
「葉かび病」は高温多湿の環境で発生しやすく、葉の裏側に灰色〜黄色のカビが生じます。



最近では抵抗品種も増えてきました。
予防には風通しを良くし、株間を適切に空けること、また朝の水やりを心がけ、夕方以降の水やりは避けることが大切です。
発生したら罹患した葉を早めに摘み取り、専用の薬剤を散布します。
「疫病」は梅雨時期に多い病気で、茎や葉、果実に褐色の病斑ができ、急速に株全体に広がります。



予防には雨よけ栽培が効果的です。
一度発生すると治療が難しいため、被害葉や被害果を早急に取り除き、広がりを防ぐことが重要です。
「青枯病」や「萎凋病」などの土壌病害は、一度発生すると対処が難しいです。
プランターで栽培している場合、これらの予防には、連作を避け、清潔な培養土を使用することが基本です。
畑での地植えでは、土まるごと全部取り替えるのはなかなか難しいので、接ぎ木で対策するというやり方もあります。
また、市販の抵抗性品種を選ぶことも有効な対策となります。
病気の予防の基本は
- 清潔な環境維持
- 適切な水管理
- 栄養バランスの良い肥培管理
の3点です。
特に種からの栽培では、清潔な土と容器を使用し、適切な間隔で植え付けることで、病気のリスクを大幅に減らすことができます。
害虫の種類と環境に優しい防除法


ミニトマト栽培では、様々な害虫が発生する可能性があります。
化学農薬に頼らない家庭菜園では、環境に優しい防除法を知っておくと安心です。
最も一般的な害虫の一つが「アブラムシ」です。
新芽や花、若い果実に集中して発生し、吸汁による生育障害や、ウイルス病の媒介を引き起こします。
初期段階では水で強く洗い流すだけでも効果があります。
また、牛乳を5倍に薄めたスプレーや、重曹水スプレーも効果的です。
「コナジラミ」は葉の裏に集まり、吸汁と排泄物(すす病の原因)で被害を与えます。
黄色の粘着シートを設置すると誘引・捕獲できます。
また、植物に無害なアルコール5%と無香料の食器用洗剤数滴を水で薄めた溶液を葉裏に散布するのも効果的です。
「アザミウマ」は非常に小さく、葉や花、果実の表面を傷つけて汁を吸います。
被害を受けた部分は銀白色に変色し、果実は傷がコルク化します。
「アザミウマ」の種類によってわかってきますが、黄色や青色の粘着トラップが誘引に効果的で、ニーム油などの天然忌避剤も利用できます。
「オンブバッタ」や「テントウムシダマシ」のような葉を食害する昆虫は、見つけ次第手で取り除くのが一番確実です。
発生が多い場合は、朝や夕方の活動時間に株元をチェックすると効果的に捕獲できます。
「ハモグリバエ」は葉の内部に幼虫が潜り込み、白い迷路のような食害痕を残します。
被害葉を見つけたら早めに摘み取って処分しましょう。
予防には、ミント、マリーゴールド、バジルなどの忌避効果のある植物との混植も効果があります。



バジルはコナジラミを寄せることもあるので、様子を見ながら行ってください。


総合的な害虫対策としては、以下のポイントを押さえると良いでしょう。
- 定期的な観察で早期発見に努める
- 天敵(テントウムシ、クモなど)を大切にする
- 忌避植物との混植で害虫を寄せ付けない
- 適切な水や肥料の管理で、健康な株を育て抵抗力を高める
- 防虫ネットなどの物理的な予防策を活用する
自然の生態系を活かしたこれらの方法を組み合わせれば、化学農薬に頼らなくても、十分に害虫対策が可能です。
よくある疑問
- 種をまいたのに発芽しません。何が原因でしょうか?
-
発芽不良には主に以下の原因が考えられます。
- 温度が低すぎるか高すぎる(適温は20〜30℃)
- 乾燥しすぎている
- 古い種で発芽率が低下している
- 種を深く埋めすぎている
- 土が固すぎる
まずは温度と湿度を適切に保ち、種を約5mm程度の浅い深さにまくことを心がけてください。
特に寒い時期は、シードヒーターや温室効果を利用して温度を確保することが重要です。
また、古い種の場合は、事前に水に数時間浸してから播種すると発芽率が上がることもあります。
- ミニトマトの苗が徒長して細く弱々しくなってしまいました。どうすれば良いですか?
-
徒長は主に光不足と水のやりすぎが原因です。
まずは直射日光は避けつつも、明るい場所に移動させましょう。
ただし、急に強い日光に当てると葉焼けの恐れがあるため、徐々に慣らすことが大切です。
また、扇風機などで優しく風を当てることで茎が丈夫になります。
徒長が進んでいる場合は、植え替え時に茎を横に寝かせて植える「横伏せ植え」も効果的です。
これにより茎から新たに根が出て、丈夫な株に育ちます。
予防としては、発芽後すぐに十分な光を確保し、適正な温度(昼25℃前後、夜15℃前後)で管理することが重要です。
水やりは、表面の土が乾いたら適度に行っていきましょう。
まとめ
種からミニトマトを育てることは、経済的なメリットだけでなく、発芽から収穫までの全過程を体験できる喜びがあります。
初めての方でも成功しやすいよう、重要なポイントを振り返りましょう。
- まず品種選びでは、初心者は「千果」「アイコ」などの栽培しやすい品種から始めるのがおすすめです。
- 種まきの適期は地域によって異なりますが、一般的には春の最終霜の2ヶ月前が目安です。
- 発芽には20〜30℃の安定した温度と適度な湿度が必要で、清潔な育苗用土と排水性の良い容器を用意しましょう。
- 苗の管理では、十分な日光と適切な水やりが重要です。
- 本葉が3〜4枚になったら植え替えのタイミングで、このとき根を傷つけないよう注意し、子葉の位置まで深めに植えると良いでしょう。
- 水やりは生育段階に合わせて調整し、特に結実期は水分不足にならないよう気をつけます。
- 肥料は植え付け前の元肥と生育期の追肥をバランス良く与えることがポイントです。
- 病害虫対策では、風通しを良くし、清潔な環境を保つことが基本の予防策です。早期発見・早期対処が鉄則で、環境に配慮した防除法も積極的に取り入れましょう。
種から育てたミニトマトは、市販の苗から育てたものより初期の成長はやや遅れますが、丈夫に育つことが多く、収穫の喜びもひとしおです。
初年度の経験を活かし、次のシーズンはさらに上手に育てられるようにしましょう。
トマトジュースのサブスクあります
- 有機栽培トマトを使っている
- 国産の
- 美味しい
トマトジュースを飲みたくないですか?
山藏農園オンラインショップではトマトジュースの定期便を販売中!
2回目以降特別価格10%オフでお届けいたします。
![飛騨高山で採れた有機栽培トマトを使って作ったトマトジュース[1ヶ月分種類お任せアソート簡易ラベル]](https://yamakura-nouen.co.jp/wp-content/uploads/2024/12/30pon.jpg)
![飛騨高山で採れた有機栽培トマトを使って作ったトマトジュース[1ヶ月分種類お任せアソート簡易ラベル]](https://yamakura-nouen.co.jp/wp-content/uploads/2024/12/30pon.jpg)
通常価格 12,000円 のところ・・・
定期便購入で2回目以降10%オフ
特別価格 10800円(税込み)
年間12回定期便でお届けした場合…
1年間で13,200円お得に!!